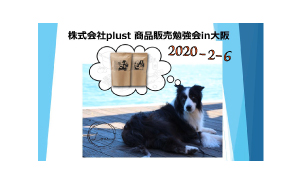GWも後半戦。すっかり暖かくなり、これからの季節、行楽地に出かける方も多いのではないでしょうか。
また最近はワンちゃんOKのホテルや施設も増えてきました。
いつもと違う空気に触れ、思い出を作るワンちゃんとの旅行は楽しいもの。
しかし車に乗ると酔ってしまうワンちゃんも珍しくありません。
元気がなくなってしまったり、吐いてしまったりというコは、遠出も難しいですよね。
そこで今日は、犬の車酔いの原因や対策をご紹介します。
車酔いの原因は?
人間と同様、犬にも耳の奥に三半規管があります。
平衡感覚を司っている三半規管が、車の揺れによって混乱し、車酔いの症状が出ると言われています。
そのほかにも、人間より嗅覚に優れていることから車の芳香剤・消臭剤・ガソリンのニオイで気分が悪くなったり、車に慣れなかったりイヤな思いをしたことがあるという「怖さ」から緊張状態になり、ストレスで車酔いを引き起こすこともあります。
車酔いのサインに注意!
犬の車酔いには、いくつか段階があります。
車に乗っている時にこんな症状があったら、車酔いに注意しましょう。
【軽度】
■吠えたり鳴いたりする
■落ち着きなくウロウロ歩き回る
■頻繁にあくびをする
■ハアハアと口呼吸をする
→初期はこのような“行動”に、車酔いのサインが表れます。
【中度】
■呼吸が荒くなる
■よだれや鼻水が出る
■体が震える
→中期になるとこのように、体調に変化が出るようになります。
【重度】
■頭を下げてぐったりする
■嘔吐
■下痢
重度になる前には、軽度〜中度の何らかの症状が出ることがほとんど。
重度になると狭い車内での対応が難しいほか犬の負担も増えるため、早めに車酔いに気づきましょう。
ちなみに上記の症状は熱中症の可能性もあります。
体を触って熱かったり舌の色が紫色になっている場合、体を冷やしながらすぐに病院に行きましょう。
車酔いを防ぐために
車酔いを防ぐため、事前にできることがあります。
■酔い止めの薬を飲む
人間同様、犬にも車酔いを防ぐ薬があります。眠くなりにくいものや抗不安作用のある薬もあるので、タイプに合った酔い止めを処方してもらいましょう。
■食事の時間を調整する
過度な空腹や満腹は車酔いにつながりやすいため、車に乗る2〜3時間前に食事を済ませるといいでしょう。
■運動
車内で眠るため、車に乗る前に適度な運動をするのもオススメです。
■クレートやゲージに入れる
窮屈に感じるかもしれませんが、車内で犬を自由にさせておくと、車内が揺れた時にバランスを取ろうとして酔いやすくなります。また急ブレーキをかけた時の危険も回避できます。扉の位置を自動車の進行方向と同じにするとさらに酔いにくくなるのもポイントです。
そのほか、ペパーミントなどのアロマを嗅がせてあげると、気持ち悪さを和らげられる効果もあります。
また運転中はゆるやかにカーブを曲がったり、こまめに空気の入れ替え・休憩も忘れずに。
犬は人間よりも芳香剤の匂いをキツく感じるため、芳香剤も取っておいたほうが良いですね。
車酔いしてしまった時は
対策をしても車酔いになってしまうことはあります。
その場合、こんな方法を試してみましょう。
■外の空気を吸わせる
気持ち悪そうにしている場合は、一度外の空気を吸わせるとリフレッシュできます。最近ではドッグランを併設したSAや施設も多いため、休憩・気分転換・水分補給・トイレも兼ねて、そういった施設を活用しましょう。走行中に空気を入れ替えることも大切ですが、その場合、窓を開けるのは鼻先が出る程度にとどめましょう。
■車内温度を下げる
車内の空気が停滞していたり、暖房で暑くなっていたりすると、より気分が悪くなります。窓を開けたりエアコンをつけたりして、車内の気温を下げてみましょう。
■ツボを押す
築賓(ちくひん:膝とくるぶしを結んだ線の中間の内側)や耳珠(じじゅ:耳の穴のすぐ前の軟骨の突起)といったツボを、やさしくつまんで揉んであげると、車酔い対策になると言われています。
口腔ケアと水分補給で、気分スッキリ
車酔いした時には、よだれが増えたり口呼吸が増えます。
また空調によって、車内は乾燥気味になります。
そのため休憩時にはこまめに水分補給をするのがオススメです。
パーラブの艶色マルチジェルは、水に垂らすだけで口腔ケアができます。
口腔ケアができれば口の中がスッキリするため、気持ち悪さを軽減できる効果も。
もちろんすべて植物由来の添加物を使用しているため、口に入れても安心。
ゴボウと同じ食物繊維が含まれているため、ストレスでお腹を壊しやすいコにもオススメです。
車でお出かけし、思い出を作るのは楽しいもの。
だからこそ色々な方法で、車酔い対策を試してみましょう。
こまめな休憩や無理のない運転は、犬の車酔いはもちろん人間にもストレスのないドライブにつながります。
ぜひ安全運転で、お出かけを楽しんでくださいね。
 ※画像クリックで商品ページへ。
※画像クリックで商品ページへ。